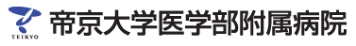大動脈解離とは

大動脈解離とは、心臓から全身へ血液を送り出す“大動脈”の内側が裂けて、血液の通り道が2つに分岐してしまうことをいいます。分岐した大動脈は、もともと3層あった壁が1層になることにより血管の壁が薄くなってしまうため、血管が破裂しやすくなり、命に関わることもあります。
このページでは、大動脈解離の概要や症状、治療方法などについてご紹介します。
大動脈解離とは?
大動脈の壁は、内側から内膜・中膜・外膜の3層構造になっています。大動脈解離では中膜が何らかの原因で裂けてしまうことにより、中膜と外膜の間に血流が入り込み、血液の通り道が2つに分岐してしまいます。このように大動脈の壁が分離してしまうことを“解離”といい、一度解離が生じると血流の影響によって短期間に解離が広がることが特徴です。
大動脈解離が生じた部分は大動脈の壁が外膜1層のみになることにより、血管の壁が薄くなります。そのため、血流によって血管が破裂する危険が高まります。血管が破裂すると命に関わる恐れもあるため、速やかな治療が必要です。

裂けた部位に応じて予後が異なる
大動脈解離は大動脈のどの部分に解離が生じたかによって、予後や治療方法が異なります。心臓から出てすぐの部位に位置する“上行大動脈”に解離が生じることを“スタンフォードA型大動脈解離”といいます。スタンフォードA型は、特に血管の破裂や
一方、上行大動脈以外に生じる場合は “スタンフォードB型大動脈解離”と呼ばれます。スタンフォードB型ではすぐに手術は行わず、まずは内科的治療を検討することが一般的です。
大動脈解離の原因
大動脈解離の発症には、さまざまな要因が関与するといわれています。以下では、主な危険因子をご紹介します。
大動脈解離の危険因子
- ・動脈硬化
- ・高血圧症
- ・喫煙
- ・ストレス
- ・高脂血症
- ・糖尿病
- ・睡眠時無呼吸症候群
- ・遺伝
など
大動脈解離にかかりやすい人とは?
大動脈解離にかかりやすい年齢は70歳代といわれています。しかし、中には40歳代や50歳代で発症する方もいます。また、先天性の病気“マルファン症候群”などによって、生まれつき大動脈の中膜が弱く、大動脈解離にかかりやすい方もいます。
なお、大動脈解離は予兆なく突然生じる傾向があります。特に発生しやすい季節は冬場で、朝6時から12時までの日中に発症しやすいといわれています。
大動脈解離の症状
大動脈解離では、大動脈の中膜が裂ける際に前触れもなく胸や背中に激痛が生じます。痛みは進行とともに胸からお腹、脚へと移動していくこともあります。また、突然意識を失う方もいます。
大動脈解離の発生直後は特に血管が破裂しやすく、発症によって血流障害が起こりやすくなるため、さまざまな合併症を引き起こすといわれています。
大動脈解離の検査方法
大動脈解離が疑われる場合には、まずCT検査を行い、中膜の裂け目や解離している大動脈の範囲などを確認します。そのほかエコー検査や胸部・腹部X線検査、心電図、造影検査、MRI検査などが検討されることもあります。
大動脈解離の治療方法
前述のとおり、大動脈解離では解離が生じている部位によって治療方法が異なります。また、どちらも発症から2週間は“急性期”と呼ばれ、病状が安定せず、急変したりすることもあるため、慎重な管理が行われます。
以下では、種類別の主な治療方法についてご紹介します。
スタンフォードA型大動脈解離の場合――緊急手術が必要
スタンフォードA型大動脈解離の場合、手術を行わなければ発症から2週間以内の死亡率がおよそ50%に達するといわれているため、速やかに手術を行うことが必要です。手術治療では解離した大動脈を切除し、人工血管に置き換える“人工血管置換術”が検討されます。この手術は、全身麻酔下の開胸手術となることが一般的です。
スタンフォードB型大動脈解離の場合――内科的治療が検討される
スタンフォードB型大動脈解離の場合、緊急手術は行わずに入院して血圧を下げるなど内科的な治療を行うことが一般的です。ただし、破裂の心配がある方や内臓への血行障害のある方では、速やかな手術治療が検討されることもあります。
急性期を乗り越えても経過観察が大切
大動脈解離では、解離の生じた位置にかかわらず、急性期後も血圧を下げる薬物療法や経過観察を行うことが大切です。経過観察ではCT検査を用い、大動脈が拡張していないか、破裂の心配がないかどうかを確認します。万一、大動脈が時間の経過とともに拡張している場合には、手術治療などが検討されます。
受診希望の方へ
胸や背中に強い痛みを感じた場合、大動脈解離はもちろんのこと、心筋梗塞や
大動脈解離の治療方法は解離の発生した部位によって異なり、急性期を脱した後も血圧の管理などを長期的に行っていくことが大切です。